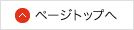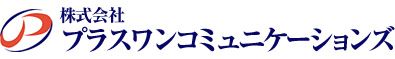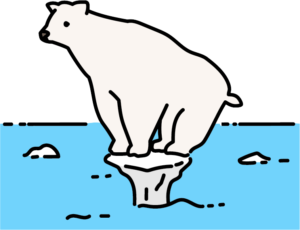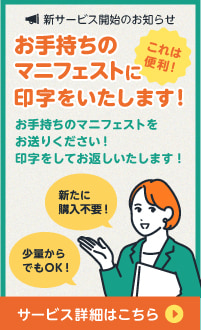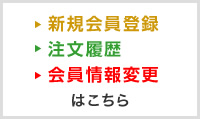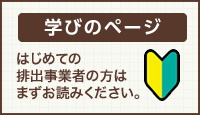3Rとは?産廃マニフェストと3Rの関係
2018年01月05日 | 豆知識

3Rとは、廃棄物を循環させるための取り組み
3Rとは、廃棄物を減らすために行なわれている取り組みの一つです。『リデュース(Reduce)』『リユース(Reuse)』『リサイクル(Recycle)』といった3つの単語の頭文字をとって『3R』と名付けられました。
3Rを意識して生活することで、廃棄物を減らして資源を循環させるための取り組みです。3Rに基づいて生活することでなぜそのような目的が達成されるのか、知っておきましょう。
リデュースとは捨てる物を減らす取り組み
リデュース(Reduce)は廃棄物の発生を減らそうという取り組みです。物を大切に使って、不要な物は買わないようにして、そもそも捨てる物を減らすといったことが当てはまります。
「安物買いの銭失い」という言葉があります。安物を買ってすぐに捨ててまた新しい物を買うから、結局お金を余計に消費していることになるという意味です。
適正価格の物を購入して長く使い続けることで、廃棄物も出費も同時に減らすことができます。リデュースに取り組むことは、節約にも繋がるのです。
リユースとは繰り返し物を使う取り組み
リユース(Reuse)は繰り返し物を使うという意味です。不用品であっても繰り返して使って、捨てないで済むようにしようという意味です。
流行っている時に買った物、その時の気分で衝動買いしてしまった物は、飽きてしまうとまだ使える物でも捨てられてしまいます。捨てる前に、機能的な部分だけ日常的に使い続ける、どうしても使わない場合は他人に譲るなどすることで、不用品=廃棄物として扱わないようにします。
リサイクルとは再資源化して再利用する取り組み
リサイクルとは、『再資源化』です。単純な再利用ではなく、廃棄物を資源として、新しい物を作り出すことを意味します。一般家庭であれば、ペットボトルを花瓶にしたり、空き箱を小物入れにしたりといった具合です。
リサイクル事業者を通して行われるリサイクルは、廃棄物を一旦『資源』の状態にして、新たな品物が作れるようにまでします。ペットボトルがフリースになる、といったように、元の形は残りません。
リサイクルは循環型社会を構築するための重要課題
3Rの取り組みは、循環型社会を形成するために推進されています。
一般家庭の3Rとして重要とされているのは『リデュース』。大量消費を防止することで廃棄物を減らすことができます。
大量消費がなくなれば大量生産されることもなくなり、結果、産廃の量も減少していきます。消費者が『リデュース』を意識するだけで、大きな効果を生みます。
産廃排出事業者が3Rの中で重要とされているのは『リサイクル』です。排出する産廃の量を減らすのが現実問題として非常に難しいでしょう。それであれば、産廃となってしまった物をリサイクル、再資源化することで、産廃としてただ処分されるだけの物を減らしていかなければいけません。
日本の産廃問題
日本は焼却場の数が世界で最も多いほど、廃棄物が多い国だと言われています。近年大きな産廃問題を耳にしないのは、日本の産廃インフラが整備しているからに他なりません。
産廃による環境汚染から発生した水俣病の歴史から、廃棄物のインフラは整備されてきています。産廃マニフェストも、産廃インフラとして採用されたシステムです。
産廃インフラが整備され、産廃問題も以前よりは減少傾向にあります。しかし、完全になくならないのが現状です。そのため次の取り組みとして、3Rが提唱されるようになりました。
日本が環境汚染問題になりにくいのは産廃インフラが整備されているから
日本は廃棄物の量が多いと言われても、信用できないかもしれません。日本よりも廃棄物まみれの国は多くあり、そうした写真を報道等で目にすることがあります。
なぜこのような事態になっているかというと、上記の通り、日本は産廃インフラが整備されているためです。報道等で目にする廃棄物まみれの写真等は、主に産廃インフラ等が整備されていない発展途上国の物が多くなっています。
発展途上国は産業だけが先走って発展してしまい、産廃インフラが整備されていません。そのため有害な産廃が適正処理されず放置されており、そのことが問題になっています。
>発展途上国のインフラについては、こちらの記事を参照してください。
産廃インフラを整備するためにも、コストが掛かります。できていないからと言って、すぐに整備するのは難しい話です。外貨獲得を推進して経済を安定させることで、産廃インフラも整備されることが期待されています。
産廃排出事業者にとっての3R
一般家庭における3Rの取り組みももちろん重要なことです。しかし、排出される量が比較にならないほど多い産廃は、一般家庭における3Rよりも重要課題となっています。
産廃排出事業者にとって、リデュースとリサイクルが最も大きな課題となります。産廃を減らし、産廃を再資源化する。この2つの取り組みで、ただ産廃として処理されるだけの産廃の量を減らすことができます。
産廃であっても一廃であっても、リサイクルのために最も重要なことは『廃棄物の正しい分別』です。
リサイクルで重要なことは『廃棄物の分別』
産廃であれば一廃であれ、リサイクルするためには廃棄物を分別することが重要です。正しく廃棄物を分別することで、再資源化できる廃棄物をまとめて処理することが可能になります。
産廃は量が多く、分別する際に掛かるコストも掛かります。そんな中、産廃業界ではリサイクルのためにロボットが活躍し始めています。
>産廃業界で活躍し始めているロボットについてこちらの記事を参照してください。
産廃リサイクルロボットはまだ日本で1台しか導入されていませんが、その活躍は目覚ましいものだと報告されています。こうしたモデルケースができれば、導入する企業も増えるでしょう。
産廃3Rのための『産廃の量・種類の把握』
産廃の3Rを促進するために重要なのは、産廃の量と種類を把握することです。どの産廃がどれだけあるのかを把握し、リサイクルできる産廃、リユースできる産廃と分けることができます。
何をどれだけ産廃として排出しているのかを把握していなければ、リサイクルできる物もリユースできる物も全て一括して『産廃』として扱うことになります。
産廃の3Rを促進することでコストダウンに繋がる
産廃排出量が多ければ多いほど、処理に掛かるコストが上がってしまいます。産廃排出事業者が3Rに取り組むことで、産廃に掛けるコストを下げることができます。
産廃は量が多いため、まとめて処理しようとすると難しいでしょう。排出される際に分別する習慣を付ける、リユースされる体制を作る等をして日々3Rを取り入れていけば、大きな作業を挟まずにコストダウンできます。
産廃を排出する時のことを考えて、日々整理していきましょう。
産廃マニフェストは3Rに活用されている
産廃マニフェストで産廃の種類や量を情報としてやり取りすることが、実は3Rの役にも立っています。リサイクルできるものの区別や減量化が可能となるのです。
産廃マニフェストの1番の目的は産廃の不法投棄や不適切処置防止ですが、そのための産廃情報がリサイクル事業にも活用され、環境保全に一役買っています。
「物を捨てるために時間やコストを掛ける」ということに疑問を覚えるかもしれません。しかし、こうして1つずつ産廃インフラを整備していくことが、住み良い環境を作り上げていきます。
※当ページの画像は経済産業省HP「3R政策」のものを使用しています。
関連記事
-
プリンタが壊れた!? マニフェスト印字を外注、「持ち込み印字」という選択肢
2025年10月06日 | トピックス
-
マニフェスト伝票はどこで買える?実は“専門店”で頼むのが一番スムーズです
-
道路が地球を救う!?環境にやさしい“未来のインフラ”の話
2025年06月25日 | トピックス
-
「暑さ」はもう他人事じゃない — 深刻すぎる“地球の叫び”
2025年06月25日 | トピックス